パキスタンハイテク技術推進プラットフォームでは、パキスタンのテック産業・企業の魅⼒を⽇本の企業様にお届けしています。今回は、2021年から2年間、JICAのICT産業振興アドバイザーとしてパキスタン現地にてテック産業・企業⽀援経験のある城ヶ﨑経営研究所の代表コンサルタントであり、株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツの取締役でもある城ヶ﨑 寛⽒にインタビューさせて頂きました。国内同業他社やオフショア企業と⽐較したパキスタンテック企業の競争優位性、取引メリット、潜在課題からその解決策まで貴重な視点をシェア頂きました。
事務局:
簡単に自己紹介をお願いします。
城ヶ﨑氏:
私は城ヶ﨑寛と申します。鹿児島県生まれの福岡県育ちで、現在は武蔵野市在住です。早稲田大学理工学部電気工学科を1987年に卒業し、IT業界では約30年の経験があります。博士(システム情報科学)の学位も持っており、2008年に中小企業診断士の資格も取得しました。
直近の経歴としては、日本アイ・ビー・エムで大企業向けITインフラ構築計画策定事業を担当した後、インドのIT企業タタ・コンサルタンシー・サービシズ・ジャパンで総合商社向けインフラ展開に携わりました。その後、英国IT企業にてベトナムオフショアリング事業の日本事業創業責任者を務め、2016年10月から独立し、城ヶ﨑経営研究所の代表コンサルタントに就任し、株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツに経営コンサルタントとして登録し、取締役を務め、2023年4月からは、山形県に新設された、電動モビリティシステム専門職大学の専任教授の職にもついています。
2021年から2023年にかけて、JICAのパキスタンICT産業振興アドバイザー業務を担当し、現地でパキスタン政府を通じて、テック産業・企業支援を行ってきました。その他にも、JICA課題別研修での「観光振興に関するデジタルマーケティング」の講師や、外務省ロシア日本センターOJT研修事業の「IT」主任講師などを務めた経験があります。
事務局:
パキスタンのテック産業・企業との出会いについて教えて頂けますか?
また、その時の第一印象はいかがでしたか?
城ヶ﨑氏:
私がパキスタンのテック産業・企業と出会ったのは、2021年にJICAのICT産業振興アドバイザーとして現地に赴任したときです。イスラマバード、ラホール、カラチという3つの主要都市を中心に、様々な大学、ICT企業、スタートアップ支援機関を訪問し、パキスタンのICT産業の実態を調査しました。
第一印象として特に印象的だったのは、想像以上に高い技術力と旺盛な成長意欲です。各社のエンジニアが機械学習、クラウド基盤、フロントエンド設計といった領域で実装ベースの実績を持ち、加えて、国内市場に閉じず国外との連携を模索している姿勢に強い成長意欲を感じました。訪問した企業の中には、すでに20年近くコマツ(小松製作所)のグローバルシステム開発を手がけているKOMATSU Pakistan SOFTや、10年以上日本本社のシステム開発をパキスタンで実施してきたSBT Pakistanなど、日本企業との長期的な協業に成功している企業がありました。
また、国立インキュベーションセンター(NIC)を訪問した際には、フィンテック、ヘルステック、エドテック、アグリテックなど多様な分野で革新的なソリューションを開発するスタートアップ企業の活気に驚かされました。特に印象的だったのは、2021年だけでパキスタンのスタートアップが過去4年間の投資総額を上回る3億5000万ドル以上の投資を調達したという事実です。
さらに、NUST(国立科学技術大学)などの教育機関では、高度な技術教育が行われており、学生たちのスキルレベルの高さも印象的でした。IPA(情報処理推進機構)のiCDを基にした調査において、ソフトウェア設計・構築・運用までを独立して行えるレベル5以上の高度なスキルを持つエンジニアの割合が、日本の5.2%に対してパキスタンでは27.6%と高水準であることが確認され、教育の成果が技術力に直結していることが見て取れました。
全体として、「知られざる宝庫」という印象を強く持ちました。これだけのポテンシャルがありながら、日本企業にはまだほとんど知られていない状況に、大きなビジネスチャンスを感じました。
事務局:
日本の同業他社や日本市場におけるオフショア企業等と比較すると、
パキスタンのテック産業・企業の競争優位性はどこにある思いますか?
城ヶ﨑氏:
パキスタンのテック産業・企業の競争優位性は主に5つの点にあると考えています。
第一に、人材の質の高さと量の豊富さです。パキスタンでは年間約2万人以上のIT技術者が輩出されており、特にAI、データサイエンス、クラウドコンピューティングなどの先端分野に強みを持っています。
第二に、コスト競争力です。他のオフショア先として人気のインドやベトナムと比較しても、パキスタンのエンジニアの人件費は競争力があります。質の高いエンジニアを低コストで確保できることは、特に中小企業にとって大きなメリットとなります。
第三に、英語力の高さが挙げられます。パキスタンは旧英国植民地であり、英語が公用語として広く使われています。これは、他のアジア諸国と比較して明確な優位性であり、国際的なプロジェクトでのコミュニケーションがスムーズに行える点が強みです。
第四に、日本との時差の少なさも重要な競争優位性です。パキスタンと日本の時差は4時間程度であり、業務時間の重複が多いため、リアルタイムでのコミュニケーションが取りやすく、開発効率が高まります。例えば、インドと比べても時差は同程度ですが、フィリピンなどの東南アジア諸国より優位性があります。
最後に、サービス分野の多様性も強みです。ウェブ開発やモバイルアプリ開発といった一般的な分野だけでなく、AIやブロックチェーン、IoTなどの最先端技術分野にも対応できる企業が多数あります。特にパキスタンの大学では、NUSTのような理工系トップ校を中心に、最新技術の研究開発が活発に行われており、産学連携も進んでいます。
こうした複数の優位性が組み合わさることで、パキスタンのテック産業・企業は日本市場において新たな選択肢として注目される価値があると考えています。
事務局:
どのようなニーズや課題を抱える日本の企業に、
パキスタンテック企業を推奨しますか?
城ヶ﨑氏:
パキスタンテック企業との協業が特に有効と思われる日本企業のニーズや課題として、以下のようなケースが挙げられます。
まず、深刻なIT人材不足に直面している企業です。日本では2030年までにIT人材が45万人不足すると言われており、特に中小企業では質の高いIT人材を合理的な賃金で確保することが難しくなっています。パキスタンには高度なスキルを持つIT人材が豊富にあり、オフショア開発によって人材不足を補うことができます。
次に、コスト削減と品質維持の両立を求める企業です。特に変化が激しく、不安定化する世界の影響で経営環境が厳しくなる中、開発コストの削減は多くの企業にとって重要課題となっています。パキスタンテック企業は、他のオフショア先と比較しても競争力のあるコストで高品質なサービスを提供できます。
また、AI、機械学習、データサイエンスなどの先端技術分野での開発ニーズを持つ企業にもお勧めです。パキスタンでは特にこれらの分野で優れた人材が多く、高度な技術力を要する開発プロジェクトに対応できます。NUSTなどの大学では国立AI研究センターが設置されるなど、先端技術への投資も積極的に行われています。
スタートアップ企業や新規事業開発に取り組む企業にも適しています。リソースが限られる中で迅速に開発を進める必要がある場合、パキスタンテック企業との協業は効果的な選択肢となります。特に、英語でのコミュニケーションが可能な環境であれば、スムーズな協業が期待できます。
グローバル展開を視野に入れている企業にも推奨します。パキスタンテック企業の多くは欧米企業との取引経験があり、国際的な開発プロジェクトのノウハウを持っています。日本市場だけでなく、グローバル市場を視野に入れた開発を行う際のパートナーとして適しています。
最後に、中長期的なIT戦略を構築し、持続可能な開発体制を確立したい企業にもパキスタンテック企業との協業をお勧めします。日本とパキスタンの間には既に20年近く安定した協業関係を維持している事例もあり、長期的なパートナーシップ構築の実績があります。
事務局:
日本企業との協業における潜在課題として何が挙げられますか?
そのための有効なアプローチ・対策は何が考えられますか?
城ヶ﨑氏:
日本企業とパキスタンテック企業の協業における潜在課題とその対策について、いくつかの重要なポイントがあります。
最大の課題は、相互理解の不足です。現状では、両国のICT産業はお互いのことをよく知らない「認知」の初期段階にあります。日本企業はパキスタンのICT産業の能力についての認識が不足しており、パキスタン企業も日本企業の求めるサービスレベルや商習慣について十分理解していません。
この課題への対策としては、まず情報交換の場を増やすことが重要です。展示会への相互参加、ビジネスミッションの実施、オンラインセミナーの開催などを通じて、相互理解を深める機会を創出することが有効です。特に2023年4月にJapan IT Week春に11社のパキスタン企業が出展したように、継続的な交流が認知度を高める鍵となります。
次に、言語の壁も大きな課題です。日本企業が外国人採用で最も重視するのは日本語力(70%)ですが、パキスタンでは日本語能力を持つIT人材が非常に少ないのが現状です。JLPT N2レベル以上の受験者数は毎年10数名程度にすぎません。
この課題への対策としては、まず英語でのコミュニケーションが可能な日本側の窓口担当者を置くことが有効です。また、日本語と英語の両方に精通したブリッジSEを活用することで、コミュニケーションギャップを埋めることができます。長期的には、パキスタンの教育機関に日本語センターを設置するなどの取り組みも始まっていますが、短中期的には言語の壁を前提とした協業モデルの構築が現実的です。
三つ目の課題は、ビジネス慣行の違いです。日本企業は詳細な仕様書や「言わずもがな」の文化がありますが、パキスタン企業は明確な指示や目標を求める傾向があります。また、日本企業が求める品質水準とパキスタン企業の標準的な品質基準にもギャップがある場合があります。
この対策としては、まず小規模なプロジェクトから始めて、相互理解を深めながら徐々に協業範囲を広げていくアプローチが効果的です。また、明確なKPIや品質基準を設定し、定期的なレビューサイクルを確立することで、期待値のギャップを埋めることができます。日本固有の商慣習や、明文化されにくい期待値を汲み取る対応が可能な企業も存在しており、たとえばSBT Pakistanは、日本企業特有の「行間」や暗黙的合意に配慮した開発体制を確立しています。そうした経験豊富な企業をパートナーとして選ぶことも一つの方法です。
最後に、パキスタンのイスラム文化への理解も重要です。礼拝の時間やラマダン(断食月)などの宗教的慣習を尊重し、プロジェクトスケジュールに配慮することが、円滑な協業関係構築には欠かせません。
これらの課題を認識し、適切な対策を講じることで、両国企業の強みを活かした相互に利益のある協業関係を構築することが可能になります。
事務局:
最後に、パキスタンテック企業との取引を検討されている
日本企業へメッセージをお願いします。
城ヶ﨑氏:
日本企業の皆様へ
パキスタンのテック産業は、日本企業にとってまだほとんど開拓されていない宝庫です。2年間の現地アドバイザー活動を通して、私はその高いポテンシャルを実感してきました。質の高いIT人材が豊富にあり、特にAIやデータサイエンスなどの先端分野での技術力は日本のエンジニアを上回るレベルにあります。コスト面でも競争力があり、時差も少なく、英語によるコミュニケーションも円滑です。
現在、日本とパキスタンのICT産業は、まだお互いを十分に理解していない「認知」の初期段階にあります。日本企業が主導的に連携体制を築くことで、現地企業との関係構築において競争優位を確保できるフェーズにあります。先行者利益を得られる可能性が高い段階だといえるでしょう。実際、コマツやSBTのように20年近く前からパキスタンでの開発を成功させている企業もあります。
もちろん、言語や文化の違いなど、乗り越えるべき課題も存在します。しかし、小規模なプロジェクトから始めて信頼関係を構築し、適切なコミュニケーション方法を確立することで、これらの課題は十分に克服可能です。日本企業の強みとパキスタンテック企業の強みを組み合わせることで、互いにとって価値のある協業モデルを作り上げることができるでしょう。
特に、今後ますます深刻化する日本のIT人材不足に対する解決策として、パキスタンとの連携は大きな可能性を秘めています。インド、バングラデシュ、ベトナムなどに続く新たなオフショア開発先として、パキスタンをぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
最初の一歩を踏み出すのは勇気が必要かもしれませんが、その先には大きなビジネスチャンスが広がっています。これまでの私の経験や知見が、少しでも皆様のパキスタンテック企業との協業検討に役立てば幸いです。
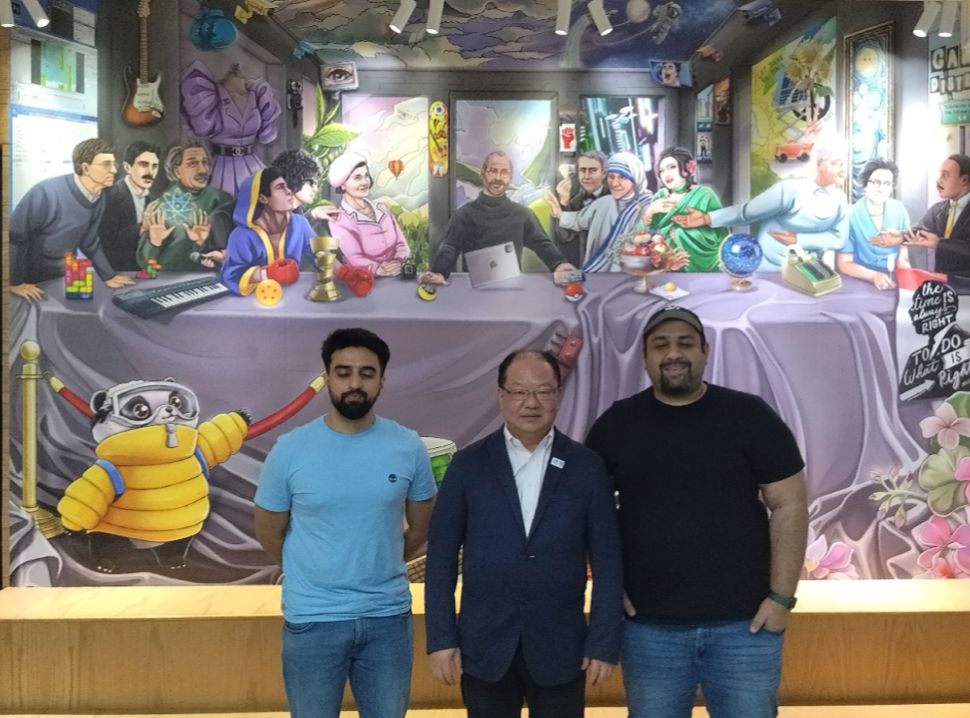
インタビュイー・プロフィール
城ヶ﨑 寛(じょうがさき ひろし)
経歴
- 鹿児島県生まれ 福岡県育ち
- 早稲田大学理工学部電気工学科 1987年3月卒業
- 中小企業診断士 2008年4月資格取得 三多摩支部 武蔵野市在住
- 博士(システム情報科学) はこだて未来大学博士後期課程 2017年3月修了
- 城ヶ﨑経営研究所 代表コンサルタント
- 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ 取締役 DX推進室長
- 電動モビリティシステム専門職大学(山形県) 専任教授
主な活動実績
- JICA パキスタンICT産業振興アドバイザー事業担当(2021年-2023年)
- JICA課題別研修(観光振興とマーケティング)「観光振興に関するデジタルマーケティング」講師
- 外務省ロシア日本センター訪日研修事業「IT」主任講師
- 外務省ロシア日本センター現地企画講座 セミナー及び Webinar 講師
IT業界での主な経験
- 日本アイ・ビー・エム:大企業向けITインフラ構築計画策定事業担当
- タタ・コンサルタンシー・サービシズ・ジャパン:総合商社向けインフラ展開担当
- 英国IT企業:ベトナムオフショアリング事業の日本事業創業責任者
連絡先:hiroshi-jogasaki@wba.co.jp

